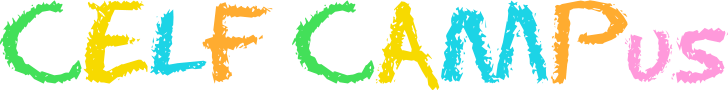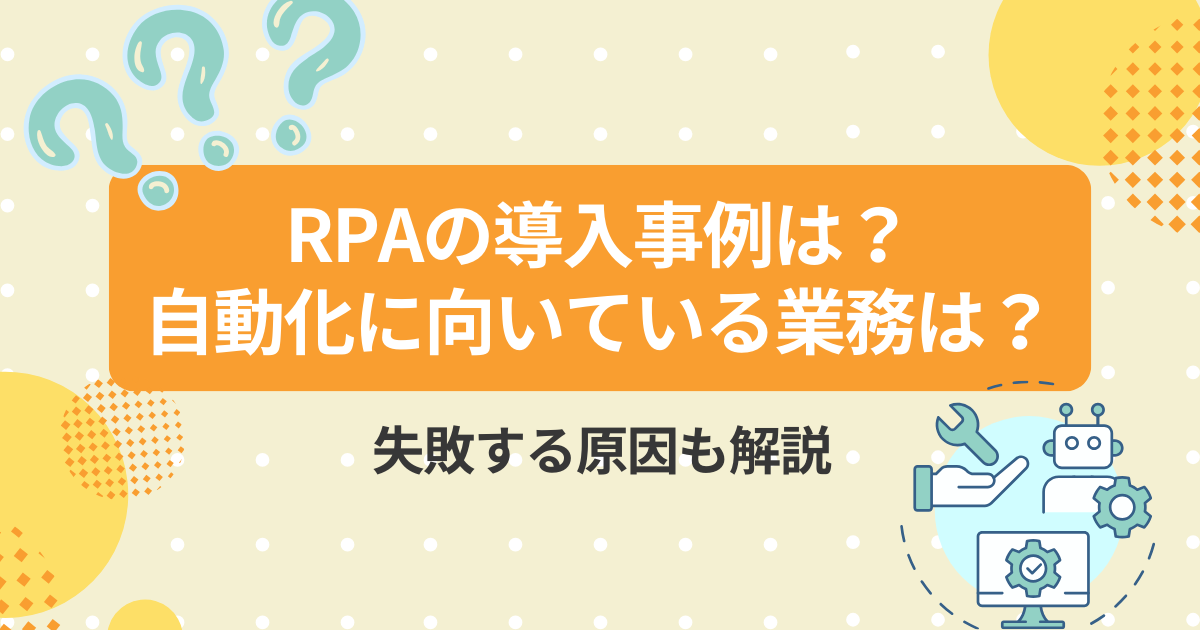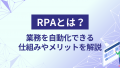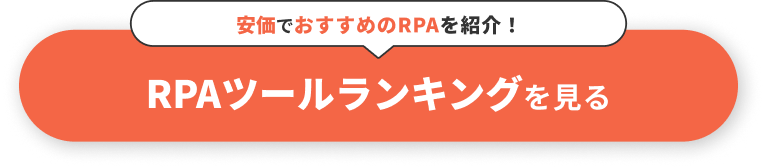RPAはさまざまな業界で導入されており、定型業務やデータ処理・収集・分析業務などを効率化します。
本記事では、RPAの導入事例や失敗事例、RPAに向いている業務・向いていない業務などを解説します。RPAの導入を検討されている方はぜひ参考にしてください。
RPAに向いている業務・向いていない業務
RPAとは、「Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略語で、ソフトウェアロボットによって業務を自動化するツールのことです。これまでパソコンを使用して人が行っていた定型業務を、ソフトウェアロボットが代替し自動化するツールを指します。
ここでは、RPAに向いている業務と向いていない業務を解説します。
RPAに向いている業務
RPAに向いている業務の代表例は、以下のとおりです。
- 定型業務
- データ処理・分析
- データ収集・加工
- 複数のアプリケーション間をまたいだ業務
- 問い合わせ業務
ルールやフローが決まっている定型業務は、RPA化が向いています。具体的には、「経費処理」「伝票処理」「決算報告書作成」などが該当します。また、「顧客情報の入力」「データ抽出」などのデータ処理や分析、Web上のニュースなどのデータ収集もRPAでの自動化が可能です。
「データの基幹システムへの登録」「受信したメール内容のExcelへの転記」などの複数のアプリケーションをまたいだ業務も、RPAが得意とする業務の一つです。さらに、よくある問い合わせへの対応はRPAが自動返信を行い、人間でしか判断できない案件のみを担当者につなげる設定にできます。
このようなRPAの活用によって、少ない人員で効率的に業務を遂行できるようになるでしょう。
RPAに向いていない業務
RPAに向いている業務がある一方で、RPA化が向いていない業務といえるのは、以下のような業務といえるでしょう。
- 例外が発生する業務
- 判断が求められる業務
- 複雑な処理が生じる業務
- ルール変更がある業務
- パソコン上で完結しない業務
RPA化が向いている「定型業務」の対極にある業務は、RPA化をしてもあまり意味がないでしょう。
つまり、頻繁に例外が発生したり、明確な判断基準がなく、その都度判断が求められたりする業務についてはRPAの活用は困難です。例えば、「顧客によって処理方法を変えなければならない業務」や「複数部門との調整が必要なプロジェクト管理」などは、RPA化に向いていません。
また、頻繁にルール変更が生じる業務も、RPA化との相性はよくありません。些細な変更であっても、作成したソフトウェアロボットの設定を変えなければならないためです。変更がある度に業務をストップさせる必要があり、手動で対応したほうが早く終わる可能性があります。
そのほか、パソコン上で完結せず、作業フローに1つでも物理的な操作が含まれている業務も、RPAを活用することは困難です。例えば、「ボタンを押す」「デバイスを接続する」といった操作が必要な業務については、手動で対応する必要があります。
【部門別】RPAの活用事例
ここからは、RPAの活用事例を部門別に見ていきましょう。
経理部門|売上・経費の集計業務など
経理部門では、「売掛・入金業務」や「買掛・支払業務」をはじめとして、「交通費確認業務」など定型業務が多く、RPA業務との親和性が高いといえるでしょう。
売掛・入金業務では消込処理や会計ソフトへ仕訳入力する作業を、買掛・支払業務では買掛金の処理業務や支払作業の効率化などについて、RPA化が可能です。また、経費精算のためのデータ突合や仕訳入力などもRPAを活用できる業務です。
人事労務部門|勤怠管理業務など
人事労務部門の「勤怠管理業務」や「給与計算業務」、「採用管理業務」も、RPAによる自動化ができます。
勤怠データの自動収集や勤怠レポートの自動生成、給与計算の自動化、応募者データの入力と管理などは、RPAを活用することで効率化が可能です。
営業部門|見積作成、営業管理など
営業部門では、「見積作成業務」や「営業管理業務」、「売上情報の集計業務」などに、RPAを活用できます。
見積作成業務ではRPAの活用により、取引先への見積金額が入ったシステムから、自動的にデータをExcelに移し、取引先にメール送付を行います。またRPA化により、受注管理システムに入っている受注情報を自動的にデータベースに取り込み、関連部門にメール送信することが可能です。
総務部門|反社チェック、書類作成業務など
総務部門ではRPAを活用することで「反社チェック業務」や「定期的な書類作成」の工数削減を図れます。
反社チェックは、インターネット検索や手作業での与信調査、登記情報調査などでも対応できます。しかし、毎月膨大な件数を調査する必要があるだけでなく、継続的に行わなければなりません。RPAツールを使えば、これらのチェック業務を自動化できます。
また、総務部門で定期的に作成する報告書についても、定型的な内容については資料作成の自動化で工数を減らせるでしょう。
全部門|日報作成・提出など
日報の作成も、RPAで自動化できます。例えば、RPAとチャットボットなどの連携により、日報を自動作成できる仕組みの構築が可能です。従業員がチャットの質問に答えた内容がそのまま業務報告になり、クラウド上にアップされます。スマホ上のアプリケーションで操作ができるため、日報を書くためにわざわざ会社に戻る必要がありません。
このようにRPAを活用すれば、さまざまな部門の業務の自動化が可能です。
「CELF」なら、プログラミングの知識がなくても、簡単に業務効率化を実現できるアプリを作成できます。お手頃価格で業務改善を始めたいなら、CELFの活用をご検討ください。
RPAの企業への導入事例
自社に導入した際の効果がイメージをしやすいように、業務システム開発ツールのRPA機能を活用して、業務の自動化に成功した3つの事例をご紹介します。
株式会社東急ストア
東急ストアは、東急グループの生活サービス事業としてスーパーマーケットを営む会社です。
東急ストアではほかのスーパーマーケットと同様に、人手不足の問題を抱えており、そのなかでどのように業務効率化を図るかが大きな課題でした。とくに、青果不良品のクレーム対応に関わる作業が大きな負担となっていましたが、SCSKの「CELF RPAオプション」を導入することで、年間で約1,000時間の作業削減を実現します。その結果、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになりました。
参考:株式会社東急ストア 様|お客様事例|PickUP ソリューション|SCSK株式会社
アイリンクス株式会社
総合通販売会社のアイリンクス株式会社では、通販業務での注文データの入力や転記作業に多くの手間がかかることが課題でした。そこで「CELF RPAオプション」を導入し、顧客別平均単価を自動で算出するアプリを作成します。これまで30分かかっていた業務がわずか4分で完了し、人的ミスも削減できました。
ニップンドーナツ株式会社
ニップンドーナツ株式会社は、ミスタードーナツと築地銀だこのフランチャイズ事業を展開する飲食店経営会社です。同社の管理部における課題は、人員が減っていくなか、手作業による事務作業が多く、非効率であることでした。
SCSKの「CELF RPAオプション」を導入した結果、これまで手作業で時間がかかっていた売上報告も自動処理で瞬時に完了するようになり、1日3時間ほどの時短を実現しています。
RPA導入の失敗事例と失敗する原因
RPAツールを導入しても、思うような効果が得られないこともあります。あらかじめ失敗事例を把握しておくことで、自社でも同じような事態に陥ることを防げるでしょう。RPAの代表的な失敗事例は、以下のとおりです。
- RPAツールを十分に活用しきれない
- メンテナンスに対応しきれない
- 業務がブラックボックス化する
それぞれの内容を見ていきましょう。
RPAツールを十分に活用しきれない
RPAツールを導入しても、現場で十分に活用しきれないと、次第に手作業に逆戻りしていく事態に陥りかねません。例えば、判断が求められる業務や定型業務が少ない部門では、RPAを導入してもメリットは少ないでしょう。
また、長時間労働が課題の部署において、その原因が「判断に時間を要する」ことである場合、業務効率化を目的にRPAツールを導入しても問題解決には至りません。RPAを導入して成果を期待できるのは、RPAと相性のよい業務を行う部門・部署であることを知っておきましょう。
メンテナンスに対応しきれない
RPAはソフトウェアロボットであり、導入後も定期的に連携ソフトのアップデートやメンテナンスが必要です。このようなメンテナンスに対応しきれなくなることも珍しくありません。
また、業務フローや作業内容に変更があったときも、ロボットのシナリオの更新を行わなければなりません。その都度リソースが割かれてしまうことを理由に、使用の継続を見送らざるを得なくなるケースも散見されます。
業務がブラックボックス化する
業務がブラックボックス化してしまい、RPAの活用がうまくいかなくなるケースです。RPAで自動化した設定や業務の内容の詳細について、RPA運用の担当者しか把握していないという状況も起こりえます。
担当者が交代した場合、後任者が設定変更やメンテナンスなどに対応しきれず、使用を止めてしまうこともあります。
RPAを導入する際のポイント
RPAを導入する際に押さえておきたいポイントは、以下の3点です。
- 導入前に自動化する業務を整理しておく
- 順序立てて自動化をしていく
- 管理する体制を整えておく
それぞれの内容を解説します。
導入前に自動化する業務を整理しておく
はじめからあらゆる業務にRPAを導入しようとすると、混乱を引き起こしかねません。導入前に、自動化する業務を整理しておくことが大切です。
事前に日々の業務の棚卸しを行い、RPAとの相性がよく、かつ自動化をするのが望ましい業務を洗い出しておきましょう。
順序立てて自動化をしていく
RPAを導入する際は、順序立てを行いながらスモールスタートで始めることが理想です。すべての業務を自動化しようとすると、シナリオ作成が複雑になるリスクがあります。
その結果、導入まで時間がかかる、導入後に頻繁にエラーが発生するといった状況に陥りやすくなります。まずは一部の業務から自動化をスタートさせ、社内にノウハウを蓄積しながら徐々に対象業務を広げていきましょう。
管理する体制を整えておく
RPAの導入にあたって、社内にしっかりと管理する体制を整えておくこともポイントです。管理・運用体制に不備があると、導入後のメンテナンスなどがうまくいかず、業務がストップしてしまうリスクがあります。
したがって、社内にRPA導入プロジェクトを立ち上げ、実際にRPAツールを運用する部門の担当者をよく心に、適切なメンバーを任命することが望ましいでしょう。
RPAの導入事例を参考に自社での活用を検討しよう
RPAを導入する際は、日々の業務の棚卸しを行い、RPAとの相性がよい業務を洗い出しておくことが大切です。
RPAの導入が向いているのは、ルールやフローが決まっている定型業務や煩雑なデータ処理や分析、データ収集などです。一方で、イレギュラーな状況が頻繁に発生する業務や判断が求められる業務、ルール変更がある業務などはRPAによる自動化は不向きであることを知っておきましょう。
初心者でも使いやすい低コストのRPAツールの導入を検討している場合は、RPA機能を搭載した、Excel感覚で業務改善アプリが作成できるノーコードツール「CELF」がおすすめです。ぜひこの機会にCELFの導入を検討してみてはいかがでしょうか。