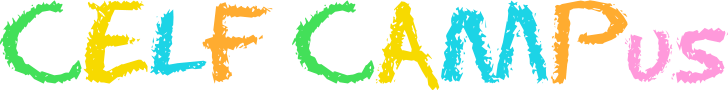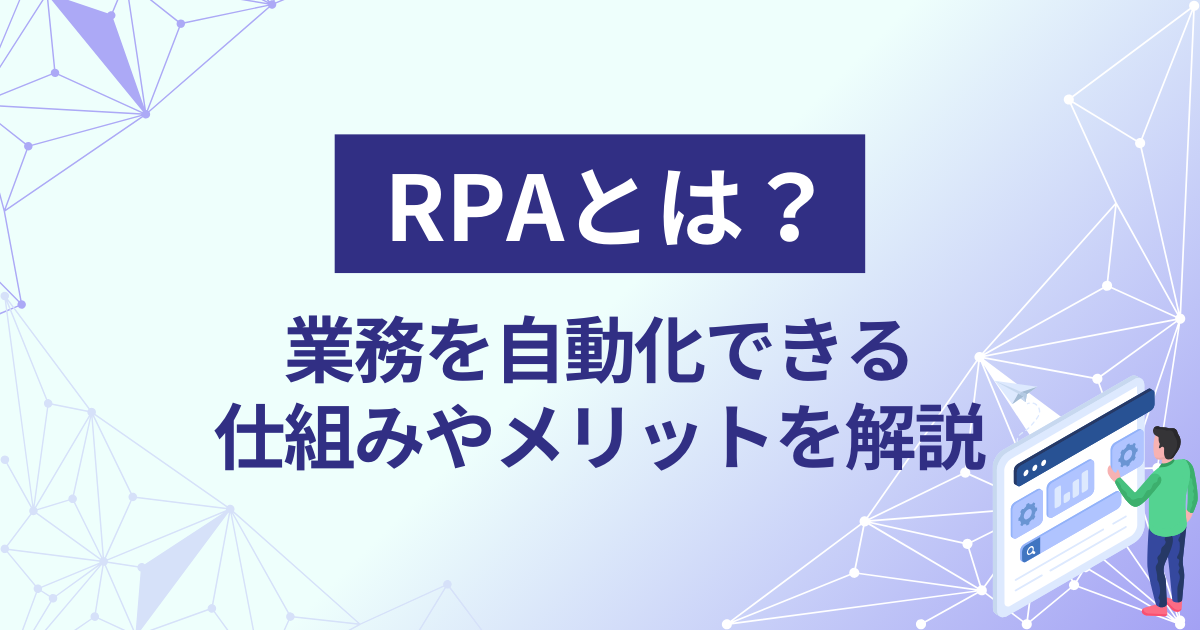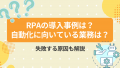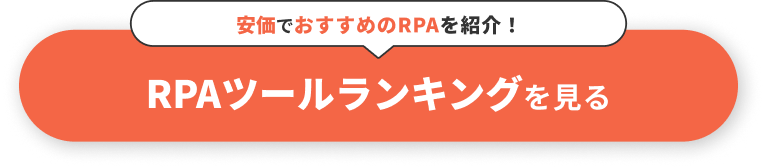RPAとは、定型業務を自動化する技術です。これまで人が行っていた業務を代替し、大幅な業務効率化を実現します。
本記事では、RPAの概要や自動化できる業務、メリット・デメリットを解説します。導入手順やツールの選び方も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
RPAとは?簡単に説明
RPAとは「Robotic Process Automation」の略で、定型的な業務を自動化する技術またはソフトウェアのことです。
ここでは、RPAの概要や自動化できる業務、AIとの違いを解説します。
業務を自動化するソフトウェアロボット
RPAとは、人がパソコン上で行っている単純作業・定型業務を、ロボットが代わりに自動化・実行する仕組みです。ユーザーが作成したシナリオに沿って自動化の作業を行います。
RPAはこれまで人が行っていたデータ入力やファイル管理など、ルールに沿った作業を自動化するため、人はより創造的で複雑な判断が必要になるコア業務に集中できます。
RPAで自動化できる業務
RPAで自動化できるのは、作業手順や流れが明確な定型業務や、毎日・毎週・毎月など、決まったタイミングで繰り返し行うルーティン業務です。
具体的には、次のような業務を自動化できます。
| 全部門 | ・データ入力・自動集計・日報作成・レポート作成・社内外システムの連携 ・ルールに基づいたチェック作業・価格調査 |
| 人事 | ・勤怠管理・労務管理・人事評価に付随する業務 |
| 経理・財務 | ・請求書の作成・発行・経費精算・資産管理 |
| 受発注 | ・在庫確認・発注リスト転記・入金確認・消込業務・買掛金処理・仕訳入力 |
| 顧客管理 | ・顧客情報の登録・インターネット上の情報収集・メール配信・問い合わせ対応 |
全部門で共通して行えるのは、データの登録・更新・変更作業です。これまで手作業で行っていたデータ入力をRPAに学習させることで、自動入力が実現します。
人事では、従業員の出勤・退勤時間を追跡し、給与計算に反映する勤怠管理業務の自動化が可能です。有給休暇消化率の定期的なチェックや、長時間勤務をしている社員へのアラートも自動で実施できます。
経理では、定期的に行う請求書の作成や発行、システムへの入力作業を自動化します。経費精算では交通費精算における一連の作業を自動化し、資産管理では減価償却の開始時・終了時に自動で通知するといった対応が可能です。
受発注では多くの業務がルーティン化しているため、自動化により大幅な業務の効率化ができます。
自動化の作業は、特に大量のデータを扱う場面で効果を発揮します。これまで人の手で多くの労力をかけていた作業を迅速かつ正確に処理でき、大幅な業務効率化を実現できるでしょう。
RPAとAIとの違い
AIも業務自動化に役立つテクノロジーですが、役割が異なります。RPAは、定型的で繰り返し行う業務を自動化する仕組みであるのに対し、AIは学習能力があり、より複雑な業務や意思決定をサポートします。
RPAはルールに従って業務を正確に実行しますが、AIはパターン認識や自然言語処理などの機能により改善を重ね、進化していきます。
そのため、RPAは単純作業・定型業務の自動化に適しているのに対し、AIは高度な分析や学習が必要な業務に向いているという点が大きな違いです。
RPAが注目されている背景
近年、RPAを導入する企業が増えている状況です。注目されている背景には、次の2点が挙げられます。
- 少子高齢化による労働人口の減少
- 技術の進化とDXの推進
詳しくみていきましょう。
少子高齢化による労働人口の減少
RPAが注目される背景には、少子高齢化で人手不足に悩む企業が増えている実情があります。人手不足解消のためには、業務効率化が必要です。RPAの導入で一部の業務を自動化できれば、多くの人数分に相当する業務を代替できます。
労働人口の減少は今後さらに加速すると予想され、RPAへの注目はさらに高まると考えられるでしょう。
技術の進化とDXの推進
RPAが注目されているのは、技術の進化により機能の高いRPAが開発されていることも理由のひとつです。DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進により、デジタル技術を導入する企業が増えており、その一環としてRPAの導入が検討されています。
DX推進は、既存のビジネスモデルを変革し、生産性を向上させることを本質的な目的としています。そのために企業は積極的にITを活用し、新しいビジネスモデルを生み出して成長していかなければなりません。RPAの導入は、このような企業の戦略に役立ちます。単純作業はRPAが代行し、人は利益に直結する業務に専念することで、生産性の向上を図れるでしょう。
RPAの仕組み
RPAは、作成したシナリオに従って自動的に作業する仕組みです。シナリオとは、RPAで自動化させたい業務の処理方法をわかりやすく示した手順書のようなものです。そのため、RPAで業務を自動化するためには、まずシナリオを作成する作業が必要になり、どのようにシナリオを作成するかで、RPAの作業品質も変わります。
作成したシナリオは柔軟に変更でき、導入後に作業内容が変更した場合でも、現場の担当が修正しながら運用できます。
シナリオはRPAが理解できるよう、コードを使って記載します。そのため、ある程度のプログラミングの知識と技術が求められるでしょう。シナリオの作成方法や難しさの度合いは、ツールによっても異なり、プログラミングの知識がなくても利用できるケースもあります。
RPAを導入するメリット
RPAの導入で得られる主なメリットは、次の3つです。
- 業務効率化による生産性の向上
- 人的ミスの防止
- 人件費などのコストの削減
ここでは、RPAを導入するメリットを解説します。
業務効率化による生産性の向上
RPAによる単純作業や定型業務の自動化により、業務を効率化できることが大きなメリットです。RPAはシナリオに沿って迅速かつ正確に業務を遂行するため、人が行う業務を大幅に削減できます。
RPAは24時間365日の稼働が可能であり、夜間や休日など、従業員がいない時間帯も業務を遂行します。
従業員は空いた時間を重要業務に集中できるため、生産性の向上につながるでしょう。
人的ミスの防止
RPAは正確に作業を実行するため、人的ミスを防ぎ、業務品質の安定化を図れることもメリットです。
単純作業は長時間繰り返すと集中力が途切れ、ミスをする可能性が高まります。定型業務に慣れてしまうと、不注意になることもあるでしょう。ミスが重なれば企業の信用に関わり、売上に影響する可能性もあります。
RPAはロボットがルールに沿って正確に作業するため、ミスを大幅に削減でき、業務品質を高めます。ミスの確認・修正に時間や労力をかける必要がなくなることも、メリットといえるでしょう。
人件費などのコストの削減
社内の単純作業や定型業務をRPAが代替することで、人件費や採用コスト、教育費などを大幅に削減できる点がメリットです。
今後、業務が増えた場合も人員を増やす必要がなく、残業のコストも減らせます。
これまで単純作業に従事していた従業員はスキルを活かしたり高めたりできる業務に従事できるようになり、仕事へのやりがいやモチベーションも上がるでしょう。その結果、離職を防止する効果も期待できます。
RPAを導入するデメリット
RPA導入では、次のようなデメリットも存在します。
- 情報漏洩のリスクがある
- RPAの専門知識を持つ人材が必要
- 複雑な処理が必要な業務には向かない
デメリットについて、詳しく見ていきましょう。
情報漏洩のリスクがある
RPAは企業の機密情報や個人情報を扱うことも多く、ネットワークに接続して使う場合は情報漏洩の可能性があります。サイバー攻撃による乗っ取りのリスクもあるでしょう。
内部でのセキュリティリスクもあります。具体的には過剰な権限付与によるデータへの不正アクセスや、不正行為による情報の漏洩などが考えられます。
これらの事態を防ぐためには、セキュリティ対策が欠かせません。定期的に提供されるセキュリティアップデートを行い、常に最新の状態にしておくことが大切です。
また、社内では最低限のアクセス権限にとどめ、IDやパスワードの暗号化をするといった対策が必要になるでしょう。
RPAの専門知識を持つ人材が必要
複雑なシナリオを作成する場合、プログラミングの基本概念の理解が必要です。RPAの専門知識を持つ人材が必要になることもあり、自社で導入予定のRPAツールを操作できる人材がいない場合は、教育が必要になるでしょう。
RPAについてまったく知識がない場合、習得には長い時間とコストがかかります。業務効率化や人件費等のコスト削減を目的に導入を考えても、目的達成には時間がかかる可能性があるでしょう。
複雑な処理が必要な業務には向かない
RPAは多くの定型業務に適用できる一方、向いていない業務もあります。多数のルール・手順がある業務や、個別の判断が必要な業務、変更が多い業務などは完全な自動化が難しいでしょう。
たとえば、企画や分析の業務は判断力が必要であり、RPAの自動化に向いていません。また、人の感性や創造力が欠かせないクリエイティブ業務も対象外です。顧客ごとに適切な対応が求められる接客業務も、RPAには適していません。
RPAツールの導入手順
RPAツールの導入は、次のような手順で行います。
- 自動化したい業務を洗い出す
- RPAツールを選定する
- トライアル期間で効果を検証する
- 本格的な運用を開始する
ここでは、それぞれのプロセスを解説します。
自動化したい業務を洗い出す
まず、自動化したい定型業務を洗い出します。そのために、自社の課題を明確にして、業務フローを可視化する作業が必要です。可視化により、「どの部分に時間がかかっているか」「改善が必要か」「自動化により効率化できるか」がわかります。自動化したい業務が明らかになれば、必要な機能もわかり、適切なツールを選べるでしょう。
さらに、自動化によって達成したい目標の設定も大切です。目標の設定により、導入後の効果を具体的に検証でき、目標に対してどれくらい達成できたかを判断できます。効果検証により課題点もわかり、シナリオを変更するなどの改善策を実施できるでしょう。
RPAツールを選定する
RPAツールはさまざまな種類が提供されており、搭載されている機能や強み、操作性などはツールごとに異なります。最初に洗い出した業務に基づき、自社に合うツールを選びましょう。
長く使うツールのため、費用対効果の確認も大切です。月額料金が高すぎると継続が難しくなり、安さだけで選ぶと目的を達成できない可能性があります。
また、将来的に必要になる機能も考慮する必要があるでしょう。
トライアル期間で効果を検証する
厳選してみても、実際に導入してみたら使いこなせなかったり、うまく効率化できなかったりすることがあるかもしれません。そのため、無料トライアルを利用し、操作性や運用のイメージを確認してみるとよいでしょう。
トライアルにより、スキル面で従業員をサポートすべき点も把握できます。本格的な運用に向けて、教育を行うなどの準備を行えることもメリットです。
本格的な運用を開始する
ツールの導入が確定したら、本格的な運用を開始します。運用しながら、作業時間の削減やミス・エラーの減少率など、具体的な指標を設定して効果検証を行いましょう。
適宜改善を行い、必要に応じて従業員の教育も実施します。運用の過程において従業員からのフィードバックも参考にしつつ、RPAツールで業務効率化を図りましょう。
関連記事:RPAの導入手順とは?メリット・デメリット、導入事例もご紹介
RPAツールの選び方
RPAツールを選ぶ際は、いくつか着目したいポイントがあります。自社に合うツールを選ぶためにも、事前にポイントを押さえておきましょう。
自社に必要な機能が搭載されているか
RPAツールを選ぶ際は、自社に必要な機能が搭載されているかの確認が必要です。提供されているRPAツールは多種多様であり、それぞれ得意とする領域は異なります。
導入の手順でお伝えしたように、自社の業務プロセスを分析し、自動化したい機能を特定することで、自社にどのような機能が必要なのかがわかります。目的に沿って、自社の課題を解決できるかという観点からツールを選びましょう。
操作性は良いか
従業員が誰でも使いこなせるよう、操作性の確認も必要です。確認する際には、直感的に操作できるかをチェックしましょう。操作性が悪いと、業務効率化の目的を達成できません。自社のITリテラシーに適しているか、専門知識がなくても扱えるかなどもチェックしましょう。
操作性に不安がある場合は、無料トライアルのあるツールを選んで試してみることをおすすめします。
カスタマイズできるか
独自の業務フローがある場合、業務に合わせてカスタマイズが可能かどうかのチェックも必要です。
ツールにはカスタマイズができる汎用型と、特定の業務に対応する特化型があります。汎用型であればカスタマイズしやすく、社内のさまざまな業務に対応できます。また、部署を横断する業務にも対応可能です。
ただし、汎用型は料金が高い傾向にあり、RPAをカスタマイズして有効活用するためには、専門知識や技術を持つ人材が必要になることも把握しておきましょう。
サポート体制が整っているか
サポート体制が充実しているかも選ぶ際のポイントです。特に導入直後は予期せぬ問題や不具合が発生する可能性が高く、自社だけで対応することは難しいでしょう。その際には迅速・適切なサポートが欠かせません。サポートの対応が遅れると、それだけ業務が停滞してしまいます。
また、RPAに慣れない従業員が多い、専門性に不安があるといった場合も、サポート体制が整っているRPAツールを選ぶ必要があるでしょう。
関連記事:RPAツールの価格はどれくらい?導入費用の相場や選び方を解説
RPAのデメリットを補うCELF
社内にRPAの専門知識を持つ人材がいない場合、教育を行うか新たに雇用する必要があります。どちらもコストがかかり、RPAを活用するまでに時間がかかるでしょう。
コストをかけず、すぐに業務効率化したい方におすすめなのが、CELFです。Excelと似た操作性で導入しやすく、RPA機能も追加できます。
ここでは、CELFの特徴や導入例を紹介します。
低コストでRPAを導入できる業務アプリ
CELFはExcelとよく似た操作性で、RPA機能を含めた業務アプリを作成できるサービスです。オプションでRPA機能を追加でき、アプリの作成と同じくRPAの作成が可能です。
Webアプリ開発機能とRPAを融合し、RPAの導入の前に必要だった業務のシステム化もできます。
CELFで実現できるのは個人の業務を自動化することで、社員が抱える個別業務・デスクワークを改善します。
コストは1台あたり年間63,000円で、小規模から導入できるのもメリットです。特定部門から導入するなど、スモールスタートにもおすすめです。
30日間の無料トライアルもあるため、使用感を確かめてから導入できます。
30日間無料トライアルのお申し込みはこちら
Excel感覚で作業できる
CELFは、いつも業務で使っているExcelと同じ感覚で使えることが特徴です。見た目や操作性はほぼExcelと変わらないため、導入時のハードルは低く、その後の運用もスムーズに行えます。
また、Excelとは異なりデータベースを使っているため、データの一元管理ができるのもメリットです。
さらに、プログラミング不要でアプリ間をまたいだデータの組み合わせも可能です。
CELFの導入事例
CELFは、中小企業から大企業まで、幅広い導入事例があります。ここでは、RPAを含めてCELFを導入した企業の事例を紹介します。
総務の働き方を改善して長時間労働を解消
情報処理事業を手がけるシステム会社・群馬農協電算センターでは、総務の仕事で長時間労働が常態化しているという課題を抱えていました。業務効率化のためにRPAツールの導入を検討し、各種ツールを比較していたところ、Excelのように操作できてRPA機能も追加できるCELFの存在を知ったということです。
テスト運用ではCELFが特別なスキル・知識を必要としないことがわかり、本格導入することを決めました。
その後、CELFを使って売掛買掛管理システムの開発を1人で行い、ノーコード開発ということもあって、2ヶ月という短期間で完成させています。
導入の結果、入力作業の手間が削減でき、残業時間を大幅に減らせました。さらに、作業漏れのミスもなくなり、業務の精度が上がったということです。
ボトムアップによる業務改善にCELFが活躍
自動車メーカー「SUBARU」グループのスバル興産では、業務改善には各部門での日常業務の改善とシステム連携が必要と考え、各部門の若手・中堅メンバーによる「業務改善プロジェクト」を立ち上げました。その際に活用したのがCELFです。
日常業務の改善では、各メンバーが「自部門の業務を、まず1つCELFに置き換える」という目標を立てたところ、工数の削減や、二重入力などによるミスを減らして業務の質全体が上げるといった成果を出しています。
CELFのRPA機能で業務効率化に成功
特装車の総合メーカーである極東開発工業株式会社では、購買課の請求書確認業務が担当者の負担となっており、効率化のシステム導入を検討していました。
費用対効果の観点でいくつかのRPAツールを比較検討した結果、選ばれたのがCELFです。導入の決め手は、他社のRPAと違って構築がシンプルだという点です。
CELFによる自動化により、1日1時間かかっていた作業時間がゼロになり、金額の記入漏れによるミスもなくなりました。自動化により、トータルで1人あたり月20時間の削減につながったということです。
RPAを上手に使いこなそう
RPAは単純作業や定型業務を自動化し、迅速かつ正確な業務を実現する技術です。人手不足の深刻化やDXの推進などを背景に、注目を集めています。業務効率化により生産性を高め、従業員はコア業務に専念できるなど、多くのメリットがあります。
しかし、RPAには専門知識がないと使いこなせないツールもあり、操作に慣れるまでは時間がかかることもあるでしょう。
初心者でも使いやすく、低コストで業務効率化できるRPAツールを探している方には、CELFがおすすめです。CELFはRPA機能に加え、ノーコードでExcelと似た操作性を持つ業務アプリを作成することができます。30日間の無料トライアルも提供されているので、ぜひお試しください。