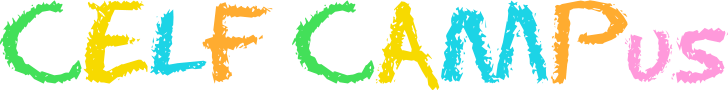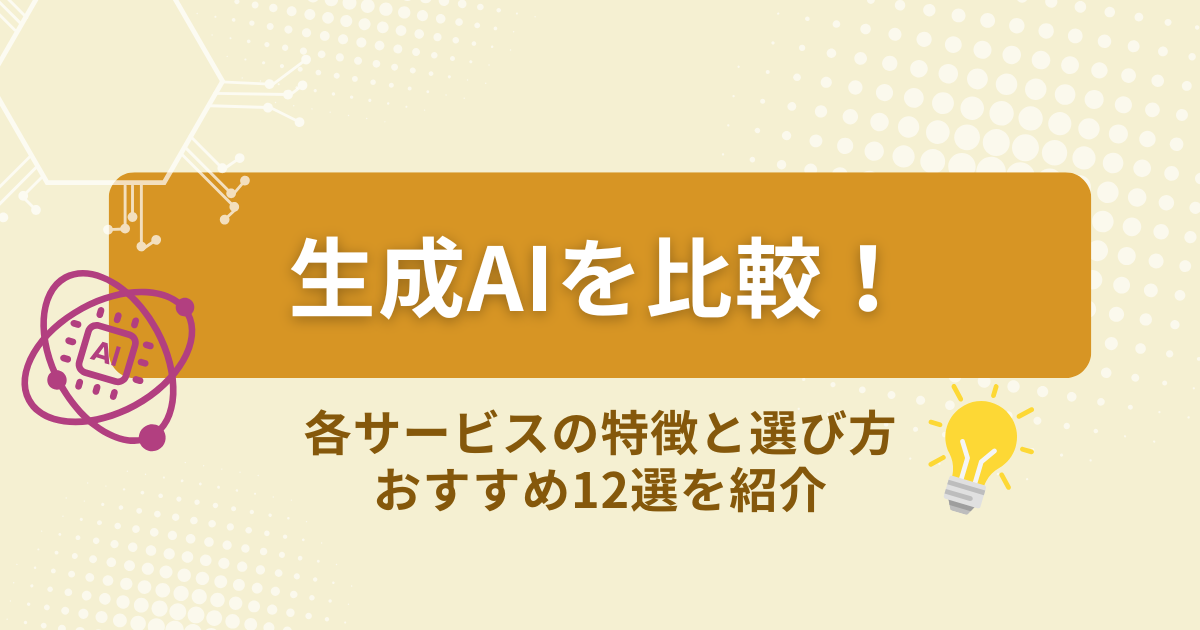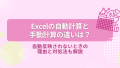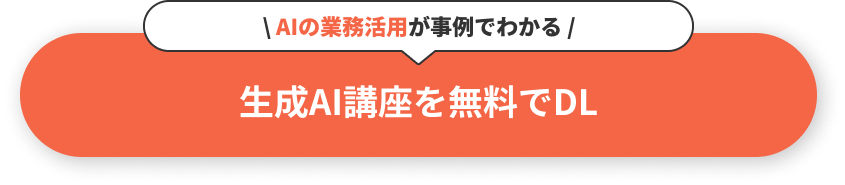文章や画像、動画など、生成AIサービスが生成できるコンテンツは多岐に渡ります。業務効率や生産性を高めるには、生成AIサービスのそれぞれの特性や強みを理解し、目的に合ったサービスを選ぶことが大切です。
本記事では、生成AIサービスの比較ポイントや使用時の注意点、おすすめの生成AIサービス12選について解説します。
生成AIは主に4種類
生成AIは、基本的に「文章生成」「画像生成」「動画生成」「音声・音楽生成」の4種類に大別されます。それぞれの主な用途や代表的なサービスは以下のとおりです。
| 主な用途 | 代表的なサービス名 | |
| 文章生成 | 報告書やメール文、ブログ記事作成・文章の要約・翻訳・対話形式の質問応答など | ChatGPT・Claude・Gemini |
| 画像生成 | Webデザイン・SNS投稿用のビジュアル作成・医療診断・芸術表現・商品写真生成・ゲーム開発など | DALL-E・Midjourney・Stable Diffusion |
| 動画生成 | マーケティング動画やプロモーションビデオの作成・教育用コンテンツの制作など | Runway・HeyGen・FlexClip |
| 音声・音楽生成 | 音楽制作・ナレーション作成・音声ガイドの作成など | VALL-E・VOICEVOX・Suno AI |
自社の業務効率や生産性を向上させるためには、各生成AIサービスの用途や特徴を理解し、適切なツールを選ぶことが重要です。
生成AIサービス12選の比較
代表的な生成AIサービスの比較表については、以下をご参照ください。
| 種類 | サービス名 | 特徴 | 日本語対応 |
| 文章生成 | ChatGPT | ・OpenAIが開発・生成AIブームの火付け役 | ◯ |
| Claude | ・自然な文章生成ができる | ◯ | |
| Gemini | ・Googleが開発 | ◯ | |
| 画像生成 | DALL-E | ・追加の微調整が簡単 | ◯ |
| Midjourney | ・高品質の画像生成ができる | ✕ | |
| Stable Diffusion | ・無料で使用可能、無制限に生成できる | ◯ | |
| 動画生成 | Runway | ・テキスト・画像で動画を生成できる | ✕ |
| HeyGen | ・AIアバターによる動画が生成できる | ◯ | |
| FlexClip | ・初心者でも使いやすい | ◯ | |
| 音声・音楽生成 | VALL-E | ・Microsoftが開発 | ◯ |
| VOICEVOX | ・日本語に特化したAI | ◯ | |
| Suno AI | ・簡単なテキストから音楽を生成できる | ◯ |
各サービスの詳しい特徴は後述します。
【文章生成AIサービス】おすすめ3選
文章生成AIサービスを選ぶ際は、以下のポイントを比較するとよいでしょう。
- 自然な日本語での文章生成や会話が可能か
- 論理的な文章を生成できるか
- 長文を処理できるか
- 既存ツールとの連携が可能か
上記のポイントを踏まえた文章生成AIサービスのおすすめ3選は、以下のとおりです。
- ChatGPT
- Claude
- Gemini
それぞれの特徴を解説します。
ChatGPT
ChatGPTはOpenAIが開発した文章生成AIで、世界中で広く利用されています。人間の会話のような自然な受け答えができるのが特徴で、質問に対して柔軟かつ的確に回答します。
無料版でも高精度な文章生成ができるものの、有料版の「GPT-4o」では、より洗練された応答と画像生成AI「DALL-E 3」の利用が可能です。
ビジネス文章やプログラミングコードの生成、翻訳、要約など幅広い用途に対応しています。ただし、最新の情報には対応していないこともあるため、事実確認を行う必要があります。
参考:ChatGPT
Claude
Claudeは、Anthropic社が開発した高性能な文章生成AIです。長文の処理に優れており、最新モデル「Claude 3.5 Sonnet」では、最大20万トークンものテキストの一括処理が可能です。そのため、大量の情報を要約したり、長文のレポートを作成したりするのに適しています。
人間らしい自然な文章を生成する能力に優れている一方、感情表現が控えめで、参考情報が少ない傾向があるといわれています。
参考:Claude
Gemini
Geminiは、Googleが開発した文章生成AIで、検索技術と連携した多機能性が特徴です。GoogleマップやYouTubeなどのGoogleサービスと統合されており、目的地の案内や関連動画の提案などが可能です。
また、GoogleスプレッドシートやGmailとも連携できるため、業務効率を向上させるツールとしても役立ちます。最新の「Gemini 1.5 Pro」は、100万トークンのコンテキストウィンドウを持ち、長文の処理を得意とします。ただし、日本語での精度にはやや課題があり、まれに不自然な表現の文章が生成されることを知っておきましょう。
参考:Gemini
【画像生成AIサービス】おすすめ3選
画像生成AIサービスを比較する際にチェックしておきたい主なポイントは、以下の4点です。
- 解像度や細部の精度は高いか
- 生成後の画像の修正や編集は可能か
- 無料で利用できるか、生成枚数に制限はあるか
- 商用利用は可能か
上記のチェックポイントを考慮したうえでおすすめの画像生成AIサービス3選は、以下のとおりです。
- DALL-E
- Midjourney
- Stable Diffusion
それぞれの特徴を解説します。
DALL·E
DALL·Eは、OpenAIが開発した画像生成AIです。高品質な画像を自動で作成できる点が特徴であり、とくに日本語でのプロンプト理解力が高い点が魅力です。生成後の微調整も可能なため、直感的に操作できます。
また、ChatGPTに統合されており、チャット形式で画像を生成・編集できる利便性も強みです。
参考:DALL·E 3
Midjourney
Midjourneyは、芸術性の高い画像を生成できる画像生成AIで、とくにリアルで精細なビジュアル表現に優れています。コミュニケーションアプリ「Discord」上で動作することが特徴です。
日本語でのプロンプト入力には対応しておらず、英語での指示が必要です。なお、無料版は廃止され、月額10ドルからの有料プランのみ利用可能となっています。
参考:Midjourney
Stable Diffusion
Stable Diffusionは、オープンソースとして提供されている画像生成AIながら、高度なカスタマイズが可能です。無料で利用できるうえ、作成できる画像数に制限がありません。
画像生成には高性能なPCやGPUが必要となり、動作環境を整えるハードルがやや高い点に注意が必要です。
【動画生成AIサービス】おすすめ3選
動画生成AIサービスを選ぶ際は、以下の4点を比較しましょう。
- 映像の解像度は高いか
- テキストや画像、既存動画などどのような入力方法に対応しているか
- 動画生成後の編集や調整はどの程度可能か
- 日本語に対応しているか
これらの点を踏まえておすすめの動画生成AIサービスは、以下のとおりです。
- Runway
- HeyGen
- FlexClip
それぞれの特徴を解説します。
Runway
Runwayは、アメリカのRunway AI社が提供する動画生成AIで、テキストや画像から新しい動画を生成でき、既存の動画の編集機能も充実しています。色味の調整やトリミング、特殊効果の追加など、動画制作を効率化する多機能ツールです。
日本語には対応していないため英語でのプロンプト入力が必要ですが、商用利用が可能であることから、クリエイターやマーケティング担当者からの高い人気を誇ります。
参考:Runway Gen-3
HeyGen
HeyGenは、AIアバターを活用した多言語対応の動画生成AIです。100以上の言語に対応し、プレゼンテーションやマーケティング動画、バーチャルイベント用コンテンツの作成に適しており、ユーザー自身の分身となるリアルなアバターを簡単に作成できます。
ただし、利用できる音声の種類が限られていることや、生成される動画がやや不自然であることに課題があります。
参考:HeyGen
FlexClip
FlexClipは、中国のPearlMountain社が提供する動画生成AIで、動画の生成だけでなく編集機能にもAIを活用できる点が特徴です。テキストの読み上げや自動字幕起こし、動画翻訳などの機能を備えています。
無料プランでも多くの機能を利用できるため、低コストで動画編集をしたい方に適しています。また、日本語に対応しているため、英語が苦手な方でも使いやすい点がメリットです。商用利用には有料プランへの加入が必要です。
参考:FlexClip
【音声・音楽生成AIサービス】おすすめ3選
音声・音楽生成AIサービスの比較ポイントとしては、以下の5点が挙げられます。
【音声生成AIサービス】
- 人間らしい自然な抑揚や感情表現が可能か
- 性質やトーンなどの細かい調整が可能か
- 日本語での生成精度は高いか
【音楽生成AIサービス】
- ジャンルやスタイルの多様性があるか
- 操作がしやすいか
上記の比較ポイントを考慮したおすすめの音声・音楽生成AIサービス3選は、以下のとおりです。
- VALL-E
- VOICEVOX
- Suno AI
それぞれの特徴を解説します。
VALL-E
VALL-EはMicrosoftが開発した高度な音声生成AIです。約6万時間分の音声データをもとに学習されており、わずか3秒の音声サンプルから話者の声をリアルに再現します。
とくに、自然なイントネーションでのテキスト読み上げやナレーション作成などを得意とし、音声コンテンツ制作の効率化が実現します。一方、精度の高さゆえに著作権やフェイクコンテンツのリスクが指摘されており、利用時には注意が必要です。
参考:VALL-E
VOICEVOX
VOICEVOXは、日本語に特化した無料の音声合成ソフトウェアで、ナレーションやキャラクターボイスの作成に適しています。イントネーションの細かい調整が可能で、多様な話者の声を選択できる点が特徴です。
商用・非商用を問わず無料で利用できるため、動画制作や音声コンテンツのナレーション用途に活用しやすいツールといえるでしょう。ただし、イントネーションが不安定になるリスクがあるため、使用前に音声の仕上がりを確認すると安心です。
参考:VOICEVOX
Suno AI
Suno AIは、テキストプロンプトを入力するだけで自動生成が可能な音楽AIツールです。特別な音楽知識がなくても、生成する曲のイメージを指定するだけで、幅広いジャンルのオリジナル楽曲を作成できます。ボーカル付きの楽曲も生成可能で、動画やポッドキャストのBGM作成にも適しています。
手軽に音楽を生成できるものの、希望する楽曲の細かいニュアンスを完全に再現するのは難しいといえるでしょう。また、AI生成楽曲の著作権に関する法的リスクがある点にも注意しましょう。
参考:Suno AI
生成AIサービスの選び方
種類を問わず、生成AIサービス全般を選ぶ際の主なポイントは、以下の5点です。
- 誰でも直感的に操作できるか
- 既存ツールとの連携が可能か
- セキュリティ対策は万全か
- サポート体制は整っているか
- 費用対効果は高いか
それぞれのポイントを解説します。
誰でも直感的に操作できるか
生成AIサービスを選ぶ際は、誰でも直感的に操作できるか確認しましょう。操作が難しいと、導入後に従業員が慣れるまで時間やコストがかかる可能性があります。そのため、誰でも直感的に操作ができ、スムーズに利用できる生成AIツールを選ぶことが大切です。
事前に使用感を試すために、無料版を試してみることをおすすめします。
既存ツールとの連携が可能か
既存ツールとの連携が可能かどうかも、生成AIサービスを選ぶ際のチェックポイントとして挙げられます。
すでに使っているツールと連携ができれば、既存のデータが利用できることから、改めて情報を入力する手間がかかりません。業務の効率化を高めるためにも、既存ツールと連携できる生成AIツールを選択しましょう。
セキュリティ対策は万全か
セキュリティ対策が万全であるかも、生成AIツールを選ぶ際に欠かせない視点です。生成AIサービスの使用時に入力した情報が流出し、第三者に漏えいしてしまうリスクがあるためです。
そのため、入力した情報を生成AIが学習に使用しない設定ができるか、データを暗号化しているかといった点をチェックしましょう。
サポート体制は整っているか
生成AIサービス全般を選ぶ際のチェックポイントとして、サポート体制の有無も挙げられます。使い方がわからないときに適切なサポートを受けられれば、導入後のスムーズな運用につながるでしょう。
すべての生成AIサービスにサポートがついているわけではありません。導入後の混乱を防ぐためにも、サポート体制の有無を事前に確認しておくことが大切です。
費用対効果は高いか
生成AIサービスを選ぶ際は、費用対効果の確認も欠かせません。高額なサービスが、必ずしも自社の業務に適しているとは限りません。導入を検討している生成AIサービスの費用とサービスのクオリティのバランスが取れているかを、確認する必要があります。
無料プランを利用すれば、気軽にサービス内容や使い勝手を確認できるでしょう。
生成AIサービスを使う際の注意点
生成AIサービスを使う際は、以下の3点に注意しましょう。
- 情報漏えいを防ぐためのルールが必要
- 出力内容を検証する
- 著作権に配慮する
それぞれの内容を解説します。
情報漏えいを防ぐためのルールが必要
生成AIサービスを使う際は、情報漏えいを防ぐためのルール策定が必要です。
生成AIサービスはデータ学習を基盤とするため、入力した情報が学習データに利用される可能性があります。したがって、顧客情報や機密情報を入力すると、情報漏えいやプライバシー侵害のリスクが懸念されます。生成AIサービスを導入する際は、機密情報の取扱いに関するルールを策定しておきましょう。
出力内容を検証する
生成AIサービスを使用するときは、出力内容の検証が欠かせません。生成AIは、ときには誤った情報を出力することがあります。
そのため、生成AIサービスが出力した内容は必ず人間が複数の情報と照らし合わせて、内容が正確であるかどうか確認しましょう。
著作権に配慮する
生成AIサービスを利用する際、著作権にも配慮しなければなりません。生成AIは与えられた情報を学習し回答を生成する仕組みのため、学習した情報のなかに著作権で保護されているコンテンツが含まれていた場合、著作権の侵害になるリスクがあります。
とくに生成AIサービスが生成したコンテンツを商用利用する場合は、事前に各サービスの利用規約を確認しておくことが重要です。
生成AIを比較して自社に合ったサービスを選ぼう
生成AIは、主に「文章生成」「画像生成」「動画生成」「音声・音楽生成」の4種類に分けられます。また、同じ用途のものであっても、サービスによって特徴が異なります。自社の業務効率や生産性を向上させるために、各AIサービスの特徴や強みを比較し、適切なサービスを選びましょう。
業務の効率化をさらに進めるためには、AIに加えて、RPAでの業務の自動化やExcelと同様の操作性のアプリが作れることが特徴の「CELF」をおすすめします。
CELFでは、30日間無料トライアルを実施しています。ぜひお試しください。
お申し込みはこちら