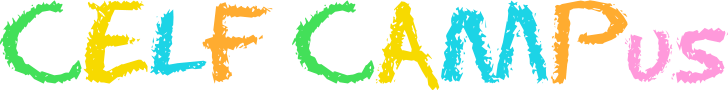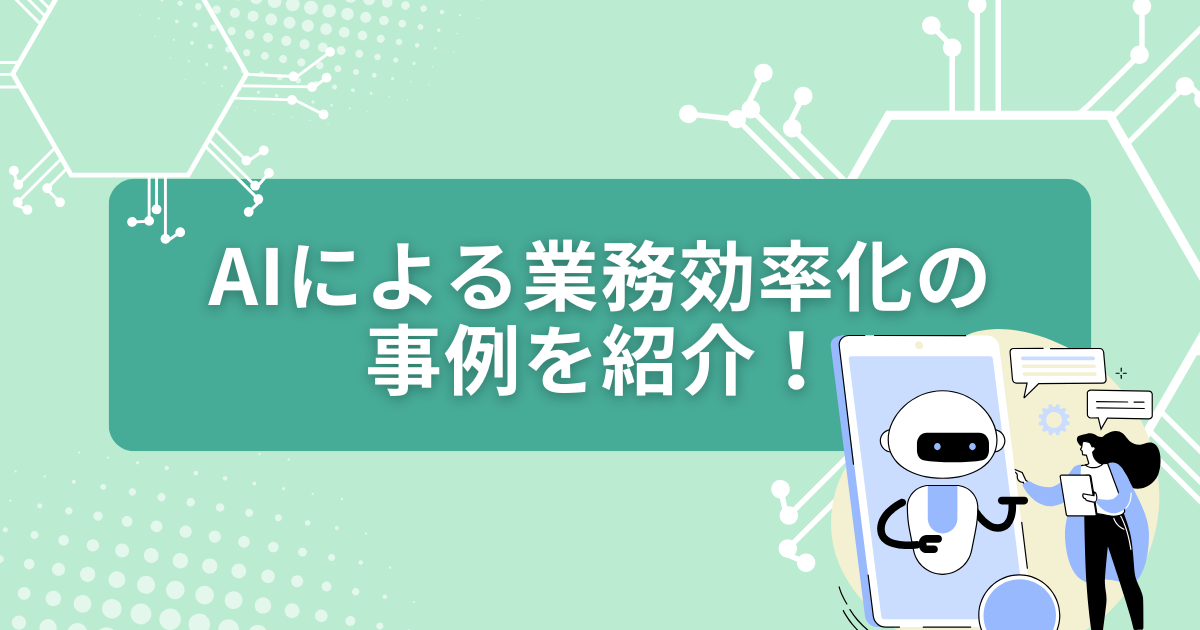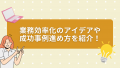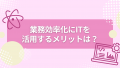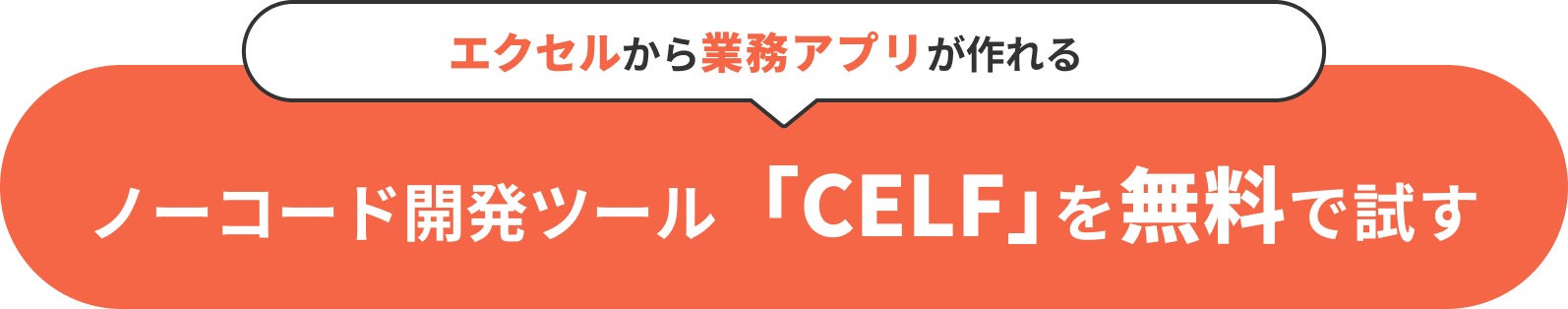普段の業務にAIを活用することで、迅速かつ正確に業務を遂行できるようになり、業務効率化を推進できます。
実際にAIを活用して業務効率化を実現した事例としては、Web申し込み専用の住宅ローンの事前診断や採用活動における選考動画の評価、社内外の問い合わせ対応への活用などが挙げられます。
本記事では、AIによる業務効率化の事例5選やAIを活用するメリット、注意点を解説します。
AIの基礎知識
AIとは「Artificial Intelligence」の略で、日本語では「人工知能」と訳されます。明確な定義はないものの、人間の思考や行動をコンピュータに実現させる技術と理解されているケースが多いといえるでしょう。
ここでは、AIの活用で業務効率化が実現できる理由やAIと生成AIの違い、AIとRPAの違いなどを解説します。
AIの活用で業務効率化が実現できる理由
AIを活用することで、膨大なデータの処理や分析、書類作成やメール作成などを自動化できます。人間がそれらの作業を行うよりも、圧倒的に速い処理速度で対応できるため、業務効率化につながるのです。
また人間の場合、業務の質を一定に保つことは容易ではありません。経験やスキルによって業務の質に差が生じるのはもちろん、体調やモチベーションなどによる影響を受けるためです。
しかし、AIには体調の良し悪しやモチベーションの変化などはありません。そのため、常に一定の業務品質を維持できます。また、ミスもほぼないため、ミスによって生じるタイムロスも削減できます。
AIと生成AIの違い
従来のAIと生成AIの大きな違いは、データの活用方法にあるといえるでしょう。
従来のAIは、データをもとに決められた作業を自動化します。それに対して生成AIは、データのパターンや相互関係を自ら学習し、新しいテキストや画像、音声などの多岐にわたるコンテンツを生成します。
AIとRPAの違い
RPAとは、ソフトウェアロボットを使用して、パソコン上の定型業務を自動化する技術のことを指します。AIとの主な違いは、対応できる業務の範囲と柔軟性にあるといえるでしょう。
RPAは、データ入力やレポート作成のように、あらかじめ手順やルールが決まっている作業を自動化できます。これに対し、AIは学習したデータをもとに識別、判断ができます。このようにAIは、RPAよりも高度な業務に対応できるのです。
AIの活用で効率化できる業務
AIの活用によって効率化できる主な業務としては、以下のような業務が挙げられます。
- 文書作成
- マーケティング業務
- 開発業務
- プロジェクト管理
- 調査・分析
- カスタマーサポート
それぞれの業務内容を解説します。
文書作成
AIを活用すれば、文書作成業務の効率化が可能です。テキスト生成や要約、翻訳などの機能を活用することで作業時間を短縮しつつ、誰でも質の高い文書を作成できます。
とくに、日々必要とされる業務で、ある程度時間がかかるようなプレゼンテーション資料やレポート、提案書の作成などで大きな効果がみられるでしょう。
たとえば、レポートは手作業で作成する場合はデータ分析やグラフ作成なども必要であり、時間や手間がかかります。しかし生成AIを活用すれば、営業データやマーケティングデータを取り込めるため、売上の分析や市場のトレンドを反映したレポートを短時間で生成できるでしょう。
マーケティング業務
生成AIは膨大な量のデータ分析と市場動向の把握を得意とするため、マーケティング戦略立案との親和性が高いといえます。
また、広告運用にもAIを活用できます。効果的なキャッチコピーや広告文の作成などについても、人間よりもスピーディーに行えるでしょう。
開発業務
AIは、プログラミングコードを使用するような開発業務にも役立ちます。生成AIはプログラミング言語の文法や一般的なコーディングパターンを学習しているため、基本的なコード構造や関数を生成できるためです。
開発者がこれらを一から作成するよりも、AIが作成したこれらをベースにアレンジや独自の機能を加えることで、業務時間の大幅な短縮が可能になるでしょう。
プロジェクト管理
AIの活用によって効率化できる業務として、プロジェクト管理も挙げられます。具体的にはプロジェクトの計画立案から進捗管理、リソースの配分まで、プロジェクト管理の一連の業務を効率化できます。
生成AIであれば、過去のプロジェクトデータやリソースの利用状況を分析し、適切なプロジェクトのスケジュール案を自動的に生成できるでしょう。タスクの優先順位づけやリソースの割り当ても瞬時に行えるため、計画案の作成に時間を割かずに済み、戦略的な意思決定やチームメンバーとのコミュニケーションなどにリソースを投下できるようになります。
調査・分析
AIを使うことで、調査・分析業務の効率化も進みます。競合調査や市場分析などは膨大なデータを取り扱うため、従来の方法だとかなりの時間と労力を費やさざるを得ません。しかし生成AIは、インターネット上の公開データや報告書、SNSの投稿など、さまざまな情報の中から自動でデータ収集を行い整理を行います。
収集したデータをもとに、トレンド分析や将来予想もスピーディーに行えるため、迅速に施策を講じられるようになるでしょう。
カスタマーサポート
カスタマーサポート業務も、AIの活用によって効率化できる業務の1つです。AIを活用したチャットボットは、頻繁に寄せられる質問に迅速に回答できます。
チャットボットを利用することで、顧客満足度の向上や、売上に直結する業務への人員の再配置などが可能になるでしょう。
AIで業務効率化を実現した企業の具体的な事例5選
AIで業務効率化を実現した国内企業の具体的な事例として、以下5つの事例をご紹介します。
- 銀行のネット住宅ローンにおける事前診断
- 電気通信事業者の選考動画の評価
- アパレル会社の商品管理
- 製菓メーカーの問い合わせ対応
- コールセンターでの入電予測
それぞれの事例をみていきましょう。
銀行のネット住宅ローンにおける事前診断
都市銀行では、Web申し込み専用の住宅ローンの事前診断をAIが行うシステムを導入したところ、従来は結果が出るまでに数日かかっていた診断が、最短1分で完了するようになりました。
AIの活用後も、審査の精度はそれまで人が行っていたレベルを担保できているとのことです。また、ローンを借り入れられる可能性が低い顧客に対して、見直しが必要な項目を提示してくれるため、再検討しやすい点もメリットです。
参考:みずほ銀行が3月23日(月)より、AI(人工知能)を活用したネット住宅ローンの簡単診断「みずほ AI事前診断」スタート! | 株式会社みずほ銀行のプレスリリース
電気通信事業者の選考動画の評価
電気通信事業者では、新卒採用選考における動画面接でAIシステムを活用しています。過去の面接動画と、それに対する採用担当者の評価を動画解析モデルで学習させ、自動で評価を行えるようになりました。
AIシステムが不合格と判断された候補者については、人事担当者が再度確認するため、選考の正確性は担保されます。
参考:新卒採用選考における動画面接の評価にAIシステムを導入~より客観的かつ統一された軸での評価を実現~ | 企業・IR | ソフトバンク
アパレル会社の商品管理
アパレル企業のECサイト向け物流倉庫では、商品の保管やピッキング、梱包までをAIロボットが担当しています。作業の完全自動化も進めており、結果的に倉庫での商品入庫の作業スピードは従来の80倍、出庫スピードは19倍にもなりました。
商品に無線自動識別タグを取り付け1つずつ区別することで、商品がどのように動いているのか、どこにあるのかを識別できるようにしています。これにより商品の入庫から検品、仕分けなどのピッキング以外の作業の自動化が実現しました。
参考:ユニクロとニトリ、超ハイテク物流の全貌 | 日経クロステック(xTECH)
製菓メーカーの問い合わせ対応
製菓メーカーではAIチャットボットを導入し、社内業務の効率化を実現しています。
同社が業務効率化のために、時間がかかっている業務を調べたところ、バックオフィス部門では問い合わせ対応に多くの時間がかかっているという結果でした。
解決策として、AIチャットボットを導入し、ポータルサイトのTOPに配置することで、AIチャットボットでの問い合わせ対応を実現しました。AIが社内の各種手続きや社内規程に関する質問に対応することで、人事部門の負担軽減を実現しています。
また、システム部門ではAIチャットボットの導入によって年間1万3000件以上発生していたサービスデスクへの電話やメールなどの問い合わせ件数を約31%削減できています。
参考:■導入事例■【Glicoグループ様】30%の社内問い合わせ対応を削減。顕在化したバックオフィスの課題を「Alli」で解決
コールセンターでの入電予測
コールセンターを運営する企業では、入電予測にAIを活用し、前年比で15%ほど工数を削減した実績があります。
コールセンターにおいて、入電予測は非常に重要な業務です。予測と実測に大きな開きがあると、実際の入電数と配置人数にミスマッチが生じ、コストやオペレーターの負担を増加させます。
AIを導入したところ、人間が行うよりも高い精度かつ簡単に入電予測ができるようになり、予測業務において工数の大幅な削減が実現しました。
参考:株式会社TMJ様|導入事例|NURO Biz(ニューロ・ビズ)
AIを業務効率化に活用するメリット
AIを業務効率化に活用することで得られる主なメリットは、以下の3点です。
- 生産性の向上につながる
- コストを削減できる
- 人手不足の解消を図れる
それぞれの内容を解説します。
生産性の向上につながる
AIを業務効率化に活用することで、生産性の向上につながります。同じ作業でも、人間が行うよりもAIが行ったほうが作業時間が短縮され、人的ミスも減らせるでしょう。
さらにAIは、人間のように体調やモチベーションによってアウトプットの量や質が変化しません。そのため、安定したアウトプットを見込めることもメリットです。
コストを削減できる
コストを削減できることも、AIの活用によって得られるメリットです。業務の自動化によって人件費を抑えられることはもちろん、教育コストも抑えられます。また、AIによる需要予測を在庫管理に活用すれば、適切な在庫管理を実現できるため、無駄な在庫コストも削減できるでしょう。
人手不足の解消を図れる
人件費の削減だけでなく、人手不足の問題を解消できることも、AIを活用するメリットです。AIは文書作成やマーケティング業務、開発業務をはじめとするさまざまな業務において、人間が行うよりも迅速かつ正確に遂行できます。
それにより、少ない従業員数でも業務を回せるようになるため、多くの企業が抱える人手不足の問題についても、AIの活用によって解消できるでしょう。
AIを活用して業務効率化をする際の注意点
AIを活用して業務効率化を進める際は、以下の点に注意しましょう。
- 情報漏洩の対策を行う
- AIのアウトプットに誤りがある可能性を考慮する
- 一時的な支出が発生する
それぞれの内容を解説します。
情報漏洩の対策を行う
AIを業務に活用する際は、情報漏洩を防ぐ対策が必須です。AIを使用して大量の個人情報を分析するような場合、AIを通じてデータが漏洩するリスクはゼロではありません。
情報漏洩のリスクがあることを考慮し、AIを使用する業務とそれ以外の業務を区別し、社内で共有しておくことをおすすめします。
AIのアウトプットに誤りがある可能性を考慮する
AIのアウトプットがすべて正しいわけではないことも、認識しておく必要があるでしょう。
不適切なデータを取り込んでいたり、データ量が足りなかったりすると、誤った情報をアウトプットする場合があります。また、AIが生成した文章や画像が著作権を侵害していることもあります。
そのため、AIを盲目的に信じることは避け、必要に応じて人間がチェックすることも重要です。
一時的な支出が発生する
AIを導入し運用するためには、コストがかかります。とくに大きな支出が発生するのは、AIの開発・導入時です。導入するシステムにもよるものの、システムの構築に多額の投資が必要になるでしょう。また、専門知識を持つ人材も確保しなければなりません。
システムが多機能であるほど高額になるため、解決すべき自社の課題をあらかじめ明確にしておき、確実に課題解決につながるシステムを導入するようにしましょう。
AI活用による業務効率化の事例を参考にしよう
AIで業務効率化を実現した国内企業の具体的な事例としては、Web申し込み専用の住宅ローンの事前診断や採用活動における選考動画の評価、コールセンターでの入電予測などへの活用が挙げられます。
AI導入前に業務を効率化をするには
業務効率化に効果的な方法をお探しなら、Excel感覚で誰でも簡単に業務改善アプリが作成できるノーコードツール「CELF」がおすすめです。煩雑なエクセル業務をシステム化して業務効率化を実現できます。
CELFでは、30日間無料トライアルを実施しています。無料トライアルでは一からアプリを開発する機能だけでなく、Excelからアプリを自動生成する機能やCELF RPAオプションを含む、すべての機能を30日間無料でお試しいただくことが可能です。