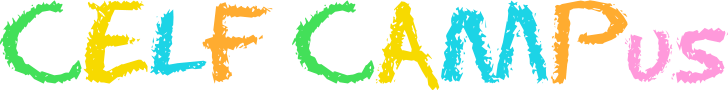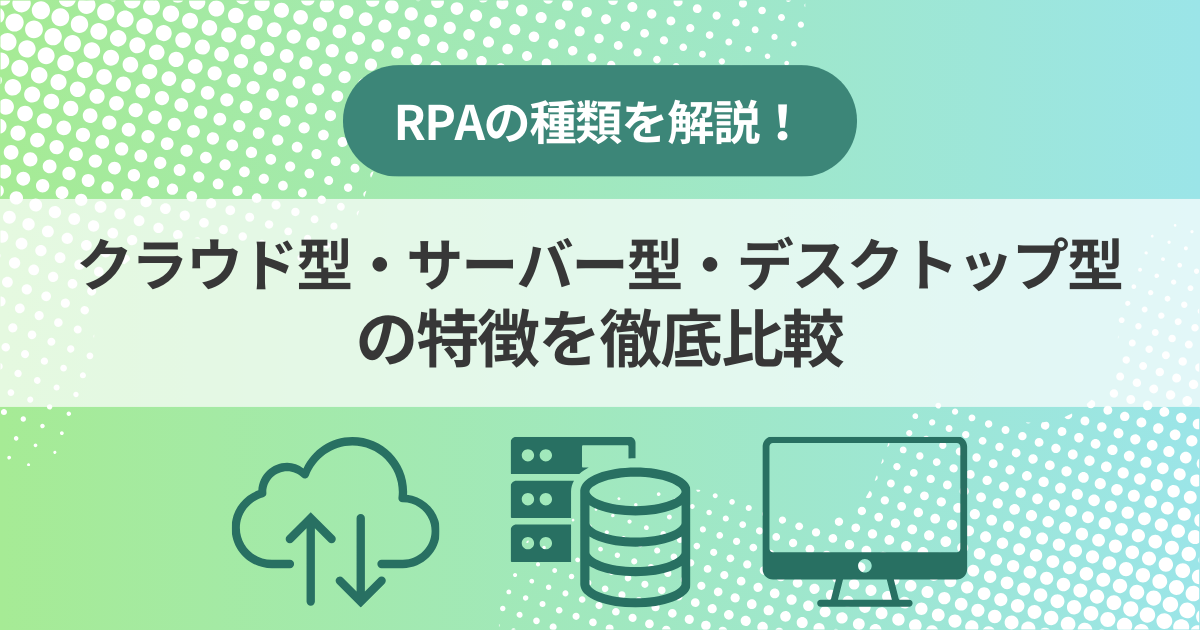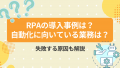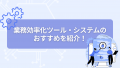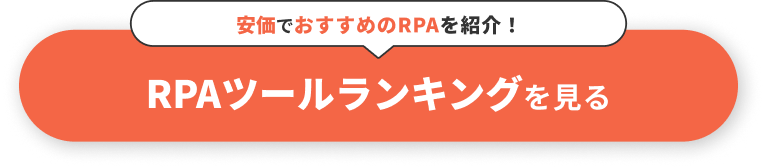RPAには、大きく分けて3つの種類があります。この記事では、RPAの3つの種類の概要およびメリット、デメリットを詳しく解説します。また、RPAを選ぶ際の4つのポイントを紹介します。本記事を参考に、自社に合ったRPAの導入を目指しましょう。
RPAの3つの種類
RPA(Robotic Process Automation)とは、RPAロボットにより業務を自動化するシステムのことです。人材不足やDX(デジタルトランスフォーメーション)化を背景に、RPAを導入する会社が増えています。
RPAには、以下の3つの種類があります。ここではまず、それぞれの特徴を確認しましょう。
| 項目 | クラウド型 | サーバー型 | デスクトップ型 |
| 特徴 | クラウドサーバー上でのRPAが稼働するため、Webブラウザ上の作業も自動化できる | ・自社のサーバーにRPAを設置 ・大量のデータ処理が可能 | ・個人または特定のPC上で作業を自動化 ・PC1台につきロボット1台が付く |
| 作業範囲 | クラウド上の作業のみ | Webブラウザ、社内サーバー、ローカル環境 | Webブラウザ、社内サーバー、ローカル環境 |
| 対応できる規模 | 小規模~大規模 | 大規模 | 小規模~中規模 |
| 導入の手間 | 比較的少ない | 多い | 少ない |
| 扱いやすさ | 比較的簡単 | 難しい | 簡単 |
| コスト | 導入するシステムや利用するサービスによって、低額~高額までさまざま | 高い | 安い |
1.クラウド型
クラウド型は、クラウドサーバー上でRPAを稼働させるタイプです。Webブラウザなど、主にインターネット上の業務自動化に最適です。
導入するシステムによって、個人事業主~大企業まで幅広く対応できます。
メリット
クラウド型のメリットは、以下のとおりです。
- 導入コストが安い
- ネット環境さえあれば比較的簡単にスタートできる
- 保守運用の負担が少ない
- Web上の作業も自動化可能
- 他の作業と同時進行できる
クラウド型は、導入するサービス内容に応じた月額使用料を支払う料金体系が一般的です。そのため、最初は少ない機能で低額からスタートできます。
ネット環境さえあれば、導入工事などが不要で比較的簡単に始められることも、クラウド型のメリットです。また、保守管理の負担が少ないのも、このタイプの特徴といえます。
クラウド型はサーバー上でRPAを稼働させるため、Web上の作業を自動化できます。他の作業と同時進行で自動化ができるため、業務をスムーズに遂行できます。
デメリット
クラウド型のデメリットには、以下があげられます。
- クラウド上以外で利用するシステムやファイルは自動化できない
- 情報漏洩のリスクがある
クラウド型は、RPAが設置されたクラウドを介してのみ自動化が可能です。そのため、クラウド外で利用するシステムやファイルは、自動化ができない点には注意が必要です。
また、クラウド上で自動化を実行するため、情報漏洩のリスクがあります。クラウド型を導入するのであれば、セキュリティに信頼がおけるシステムを選びましょう。
2.サーバー型
サーバー型は、自社のサーバーにRPAを設置するタイプです。サーバーの管理や実行、指示は、社内の管理者が行います。
サーバー内で一元的に自動化を実施するため、大量のデータ処理が可能です。また、クラウドサービスとローカルアプリケーションのどちらにも対応しているため、幅広い業務を自動化できます。
メリット
サーバー型のメリットは、以下のとおりです。
- 大量データの一括処理が可能
- 100体以上のRPAロボットによる大規模展開が可能
- セキュリティが高い
サーバー型は、サーバー上にRPAを構築することで、1台のパソコンに対し100体以上のロボットが作動できます。大規模展開にも対応可能で、大企業における業務自動化でも利用されています。
また、サーバー型はセキュリティ性が高いことも特徴です。サーバーの内部にRPAを構築するサーバー型は、クラウド型やデスクトップ型と比較し、情報が外に漏れるリスクが少ないとされます。
そのため、セキュリティが高いシステムの導入が必要な場合は、サーバー型は有力な選択肢となるでしょう。
デメリット
サーバー型のデメリットは、以下の2つです。
- コストが高い
- 導入と保守運用の手間がかかる
サーバー型は、導入に費用がかかる点に注意が必要です。サーバー型を導入するのであれば、見積もりを取り予算に合ったシステムを選びましょう。
また、導入や保守運用のハードルが高く、手間がかかります。そのため、専門のIT管理部門を設け、運用していく必要があるでしょう。
3.デスクトップ型
デスクトップ型はパソコンごとにRPAをインストールし、パソコンごとに業務の自動化を行います。そのため、パソコン内の事務作業を個別に自動化するのに向いています。
パソコン1台からスタートできるため個人や中小企業、スモールスタートしたい企業に向いている方法といえるでしょう。
メリット
デスクトップ型のメリットは、以下のとおりです。
- 初めてのRPA導入にも向いている
- ITの専門知識がなくても利用しやすい
- パソコンごとに業務の自動化が可能
デスクトップ型は、小規模からスタートできます。クラウド型やサーバー型と比較して価格も低めなため、初めてRPAを導入する方でも始めやすいでしょう。
また、それぞれのパソコンにRPAを導入し自動化をするため、ITの知識がなくても始めやすいといわれます。パソコンの知識に不安がある方や、IT管理部門の設置が難しい方は、デスクトップ型が選択肢となりそうです。
デメリット
デスクトップ型のデメリットは、以下のとおりです。
- 属人化する可能性がある
- 担当者の異動や退職時の引継ぎに手間がかかる
デスクトップ型は、各担当者がパソコンごとに自動化を実施します。そのため、属人化する可能性には注意が必要です。担当者が異動や退職をする際に引継ぎがうまくいかない、次の担当者が思うように使えないといった事態が発生するかもしれません。
デスクトップ型を導入するのであれば、属人化を防ぐマニュアルや運用ルールを定めることが重要です。
RPAの種類を選ぶ際のポイント
ここからは、RPAの種類を選ぶ際に確認するべき以下の4つのポイントを解説します。
- コスト
- 操作性
- サポート体制
- 無料トライアルの有無
RPAには、さまざまな種類があります。導入を検討しているのであれば、いくつかの種類を比較検討し、自社に合ったものを選びましょう。
1.コスト
RPAを選ぶポイントの1つ目は、コストです。RPAを利用するには、導入コストとランニングコストがかかります。導入する目的や規模が大きくなるほどコストが上がる傾向があるため、まずは必要な機能や導入する範囲をしっかりと見極める必要があるでしょう。
なお、クラウド型は導入コストを比較的抑えられるものの、ランニングコスト(月額使用料)は高めです。サーバー型は、導入コストとランニングコストともに高額です。システムによっては、導入だけで100万円を超える費用がかかることは押さえておきましょう。
デスクトップ型は、クラウド型やサーバー型と比較すると、低いコストでの導入が可能です。まずは少ないコストから始めたい方は、デスクトップ型が選択肢となるでしょう。
2.操作性
RPAを選ぶポイントの2つ目は、操作性です。RPAを使用するスタッフのすべてが、ITの専門知識を保有しているとは限りません。
いくら良い機能があるRPAだとしても、社員が操作できなければ意味がありません。導入にあたっては、自社で使いこなせるシステムであるかも重要なポイントとなるでしょう。
なお、先述のとおりサーバー型の運用には、運用および保守、管理を請け負うIT専門部署が必要です。サーバー型の導入を希望するのであれば、まずは社内の体制を整えることからスタートしましょう。
3.サポート体制
ポイントの2つ目は、サポート体制です。RPAを導入するのであれば、充実したサポート体制が整っている会社を選びましょう。
サポート体制が充実していれば、不明点や不具合が出たときにも安心です。土日や夜間に営業している会社であれば、その時間にサポートを受けられるかについても事前に確認しましょう。
サポートには電話やメール、チャットツールなど、さまざまな方法があります。システムによっては、出張サポートも用意されています。社内にIT人材がいない会社であれば、特に自社に合った手厚いサポートが受けられるシステムを選ぶことが重要です。
4.無料トライアルの有無
ポイントの3つ目は、無料トライアルの有無です。RPAシステムの導入には、手間もコストもかかります。そのため、一度RPAを導入すると、たとえ機能やサービスに不満があってもすぐに変更することは難しいでしょう。
納得がいくRPAの導入を実現するには、無料トライアルによって機能やサービスを確認できると安心です。RPAを導入するのであれば、まずは無料トライアル期間を活用し、使いやすく満足できる機能があるツールを選びましょう。
無料トライアルがあるRPAシステムを希望するのであれば、次項で解説するCELFがおすすめです。どのRPAシステムを選べばよいかわからないと感じる方は、ぜひ一度CELFを検討してみてください。
表計算をRPA化するならCELFがおすすめ
表計算に関する業務を自動化したいと考えているのであれば、CELFがおすすめです。CELFとは、普段使用しているExcelファイルをノーコードで業務アプリ化できるシステムです。
CELFを活用することで、効率的なデータの収集や分析が可能になります。概要を、以下で確認しましょう。
| CELF(クラウド版) | |
| 1年間利用する場金額目安 | 63,000円(RPAオプション:税抜4.2万円/年<1台>、CELFクラウド版:税抜2.1万円/年<1ユーザー>) ※ただし「CELFクラウド版」最低利用ユーザー数は10ユーザーとなるため、上記の金額となるためには10ユーザー分以上の申込みが必要です ※RPAオプションは1台から利用可 |
SCSK株式会社の「CELF」のクラウド版は、年間利用料金2.1万円(税抜)/1ユーザーに、RPAオプション4.2万円/年(税抜)を追加して利用できるRPAツールです。初期費用が不要で、低コストでRPAツールの運用を始められます。
CELFでは30日間無料トライアルを実施しております。
CELFの無料トライアルにお申込みいただくと、1からアプリを開発する機能だけでなく、Excelからアプリを自動生成する機能やCELF RPAオプションを含む、全ての機能を30日間無料でお試しいただけます!
30日間無料トライアルのお申し込みはこちら
自社に最適なRPAの種類を選び、業務の効率化を目指そう
RPAとは、RPAロボットにより業務を自動化するシステムのことです。人材不足やDXの推進、業務効率化を目指す企業を中心に、RPAの導入が増えています。
RPAにはクラウド型およびサーバー型、デスクトップ型があります。どの種類を選ぶかによって、コストや導入の手間、対応できる規模などが異なるため、自社に合ったものを選ぶことが肝心です。
RPAの中には、無料トライアルを設けているものもあります。無料トライアルを活用すれば、契約前に使用感や使い勝手を確かめられます。RPAの導入を検討している方は、ぜひ一度無料トライアルをお試しください!